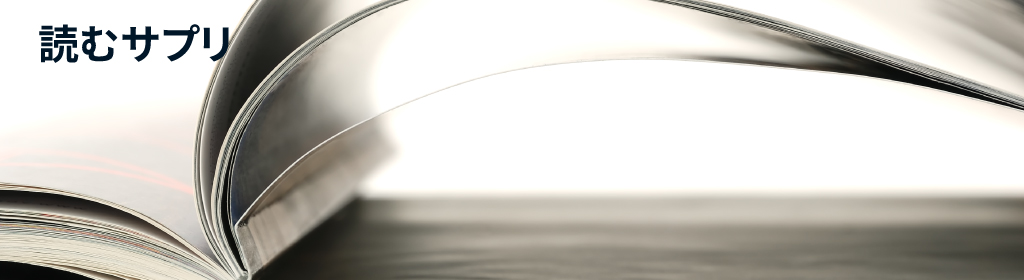第28回 生体がもつ学習能力
1974年、米国の心理学者ロバート・エイダーは、ある実験によって当時の医学会の常識をくつがえしました。
当時の医学会では、経験に反応して行動を変える能力を持つのは、脳と中枢神経系だけであるというのが常識でした。
エイダーが行った実験は、次の2段階で進められました。
まず、血中で病気と戦うT細胞の量を人為的に減らす薬をサッカリン水に混入して白ネズミに投与。
次に、同じ白ネズミにT細胞を減らす薬を入れずにサッカリン水だけを与えました。
それでも白ネズミの血中のT細胞の数は減少し、病気にかかったり、死亡したりするネズミも出てきたのです。
白ネズミの免疫系は、甘い水に反応してT細胞の量を減らすことを学習したのです。これは、当時のいかなる科学的知識に照らしても、起こるはずのないことでした。
この実験が立証したことは、人間の情動が免疫系に直接インパクトを与える物理的経路が存在するということです。つまり、感情や気の持ち方が身体に影響を及ぼし、病気になることも、逆に病気を治すこともあるのです。