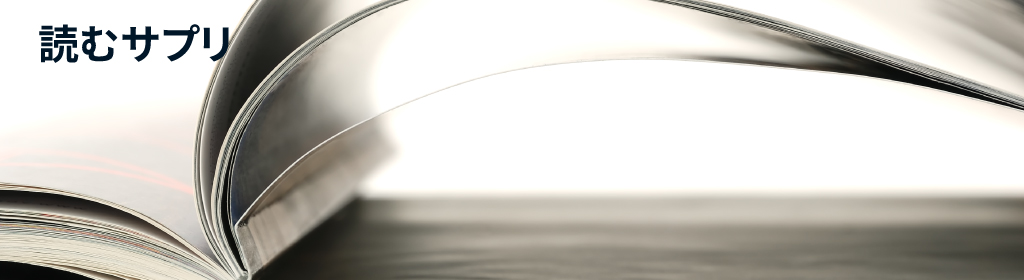第29回 表に出ない不満を察知する
4世紀末から5世紀前半に在位したと推定されている日本の第16代天皇の仁徳天皇はその業績から聖帝とも称されています。
その仁徳天皇はある時、人家のかまどから炊煙が立ち上っていないのに気づきました。そして租税を免除し、その間、自らは倹約に努めたといいます。
かまどの煙の有無を見ただけで、民衆の苦労を「察知」したのです。
一つの事象を見て、何に気づくことができるか、その感性が求められるのは、政治もビジネスも同じです。
ストラパック株式会社(東京都)は、段ボール箱にひもなどを自動で結ぶ梱包用装置のトップメーカーです。
同社がトップメーカーとなった契機は、1974年に「油のいらない新製品」を開発したことだそうです。それまで、同種の機械は油が装置に付着し段ボールに油が染み込みむという不具合が頻発しており、同社はこれを解決したのです。
同社は業界トップを維持するために、顧客からのクレームを製品開発に活かしているといいます。
たとえばスペア部品の場合、出荷量で一番多いものに注目する。なぜなら「頻繁に部品が交換される」=「耐久性や利便性の問題が隠れている」と判断するわけです。
このように、同社は表に出てきにくい「裏の不満」を察知する仕組みを持っています。
民が貧しいから、炊煙が立たない。耐久性に問題があるから部品交換が頻繁に起こる。という具合に、原因と結果の関係を見抜く力は、政治においてもビジネスにおいても不可欠な要素です。