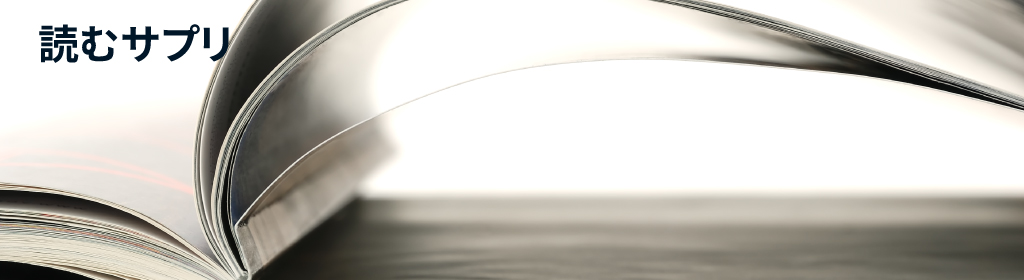第33回 「ヒューリスティック」とは?
私たちは日々の判断や意思決定を、すべて理性的に行っているわけではありません。多くの場合、過去の経験や印象、直感などをもとに「すばやく判断するための近道」を使っています。これを「ヒューリスティック」(判断の簡便法)」といいます。
たとえば、かつてNHKの番組で行われた実験では、通行人にハサミの値段を当ててもらいました。参加者は予想の前に、200から2000まで200刻みで数字が書かれたルーレットを回し、その出た数を記録しました。その結果、小さい数字(200~1000)を出した人の平均推定額は937円、大きい数字(1200~2000)を出した人の平均は1679円となりました。さらに、高い価格をつけた人は「高級そう」「よく切れそう」と肯定的に評価し、安いと感じた人は「100円ショップで売っていそう」と否定的に評価する傾向が見られました。
このように、最初に示された数値(アンカー)が後の判断に影響を及ぼす現象を「アンカリング効果」といいます。これは、ヒューリスティックの一種であり、人間の意思決定に深く関わっています。
ヒューリスティックには、主に次の5つのタイプがあります。
① アンカリングと調整:最初の値を基準にして判断が引きずられる。
② 入手可能ヒューリスティック:思い出しやすい出来事ほど頻繁だと誤認する。
③ 代表性ヒューリスティック:短期的な情報から全体像を決めつけてしまう。
④ 感情ヒューリスティック:好悪の感情が判断を左右する。
⑤ 大勢順応性ヒューリスティック:他人の行動に流されやすくなる。
ヒューリスティックは、私たちが限られた時間や情報の中で素早く決断するための有効な手段である一方、思い込みや偏見による誤判断を招く危険もあります。その仕組みを理解することが、より的確な判断への第一歩といえるでしょう。