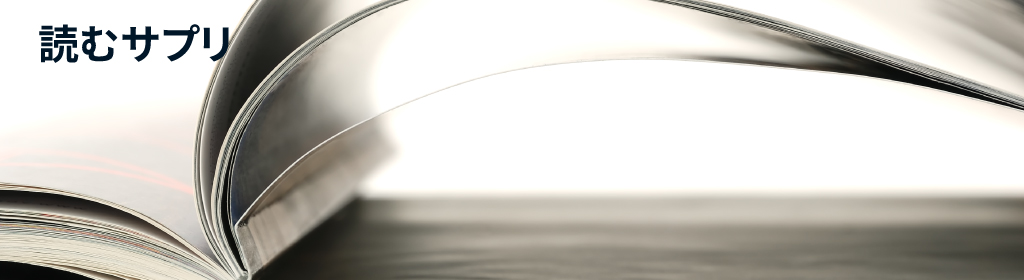第34回 「リスク認知のゆがみ」と選択誘導
私たちは日常の中でさまざまな危険や不安に向き合っていますが、それらを必ずしも客観的に捉えているわけではありません。心理学では、人が無意識のうちに危険を大きく見積もったり、逆に過小評価したりする傾向を「リスク認知のゆがみ」と呼びます。
災害のニュースを見た後に急に不安が高まったり、これまで問題がなかったという理由だけで安心してしまったりするのは、その典型例です。こうしたゆがみは恐れすぎないための自然な心の働きである一方で、判断を歪める要因にもなります。
この心理的傾向は、住宅や建材といった高額商品を扱うビジネスにおいて、無視できない影響を持ちます。消費者は「安全性」や「性能」といった専門的な情報を、自分の感覚や経験を手掛かりに判断します。そのため、商品そのものの性能だけでなく、情報の提示方法や選択肢の示し方によって、選ばれる商品が変わってきます。
たとえば耐震性能の提示においても、「認知のゆがみ」は顧客の選択に反映されます。次の2つの提示方法は、実質的にはまったく同じ二択であるにもかかわらず、消費者の反応は大きく異なり、意思決定に影響を与えます。
①建築基準に合う耐震性の住宅を標準仕様(2000万円)とし、ワンランク上の耐震性の住宅(2500万円)をオプションにする。この場合、多くの人は「標準なら問題ない」と考え、基準レベルの住宅を選びやすくなります。
②ワンランク高い耐震性の住宅を標準仕様(2500万円)とし、建築基準レベルの住宅(2000万円)をオプションにする。この提示では、標準より性能を下げる選択に心理的抵抗が生まれ、「少し高くても上位性能を維持したい」と考える人が増えます。
このように、選択肢の本質は同じでも、“標準”という位置づけや「性能を下げる」という印象が判断を揺らし、選択の方向を変えるのです。
行動経済学が示すこの視点は、商品の価値を誠実に伝えつつ、顧客が自分に合った判断をしやすくするための有効な手がかりとなります。